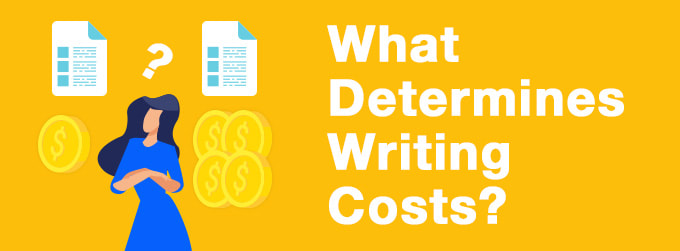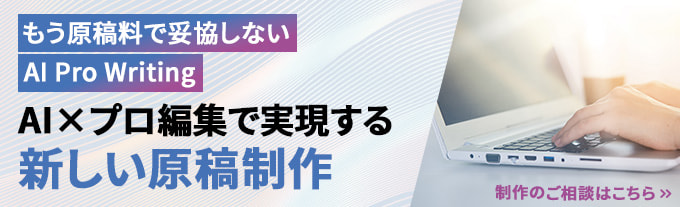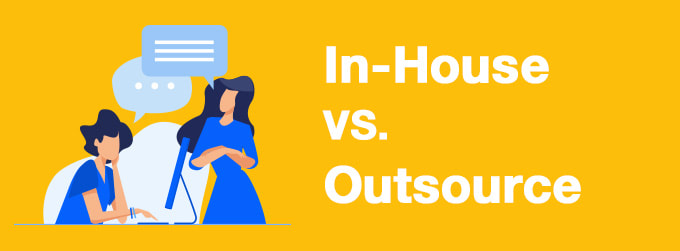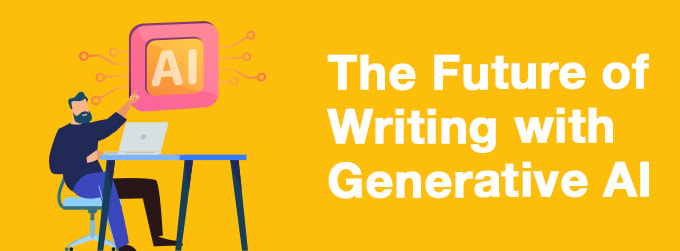コンテンツ制作において原稿料は非常に幅がある
コンテンツマーケティングではコンテンツの内容や企画、品質は重要です。しかし、特に気をつけなければならないのはコストです。コンテンツマーケティングは短期的な成果が得られにくく、しかも費用対効果が算出しづらい取り組みです。コストに対してもシビアにならざるを得ず、そのため、ライターへの原稿料をなるべく適正な価格で依頼する必要があります。
しかし、ライター、制作会社、代理店などへ依頼する際に、原稿制作の費用に関してどのくらいを目安として捉え、どのように見積もればよいのかという疑問が湧くかもしれません。
その理由の1つに、原稿制作には決まった相場がないためです。例えばWebメディアの1記事の一般的な分量である2500-3000文字程度の記事執筆を依頼したとします。ものによっては1万円以内で依頼できるものもあれば、十数万円以上かかるものもあります。
これはなぜでしょうか?思いつく理由として、多くの製品がそうであるように、「品質の違い」が挙げられると思います。皆さんも日常生活の中で値段が高いものを買ったら品質が良く満足したけど、安物を買ったら品質が悪く役に立たなかった、という経験はあるかもしれません。
確かに原稿にも「良い」「悪い」というものは存在しており、値段を左右する重要な要素です。しかし、それは本質的ではありません。大事なのは、なぜ品質に良し悪しが生まれるのかという要因とコスト構造を理解することです。以下、この点に関して詳細に解説していきます。
原稿制作に「ライター以外」の工程があるか
結論を先にいうと、原稿料に幅がある大きな理由(品質に差が生じる理由)の1つは、原稿の制作工程にライター以外がどれだけ関与しているかが異なるからです。制作業界以外の方はあまりイメージしにくいかもしれませんが、世の中にあるWebメディア、雑誌、新聞などの記事はライター一人の力では完成しておらず、裏にはさまざまな人が関与します。
一般的に、Webメディアの記事であれば「ライター」、紙の新聞であれば「記者」と呼ばれる職業が取材などで情報を集めたうえで原稿を執筆します。こうしてでき上がった原稿は、前者では「編集者」、新聞社などであれば「デスク」と呼ばれる職業によって文章が手直しされ、記事の種類や出版物によっては、「校正」や「校閲」と呼ばれる別の作業者のプロセスを経てようやく世の中に公開されます。
たまに、少し物議を醸すWeb記事の内容や攻めたタイトルの記事が世の中に出て、それがSNSなどで誰かが取り上げて盛り上がる(炎上する?)ことがあります。そこでは、「このライターは何トンチンカンなことを書いてるんだ!?」と指摘する光景を目にします。こういう指摘が散見されるのも、世間は「記事はすべてライターが書いている」という思い込みがあります。
特にメディアはクリックさせて読んでもらうために、かなり“攻めたタイトル”をつけることがよくあります。ですが、そうしたタイトルは、私の肌感覚ではライターはほぼ関与していないと見ていただいても概ね間違いないと思います。
いずれにしても重要なのは、ライターが記事のベースを作り、編集者などがそれをブラッシュアップすることで優れた記事が生み出されていくということです。さらに、優れた記事が生まれるには、それはそもそものテーマ選定や企画、ストーリーラインも重要です。これはライターが考えている場合もありますが、編集者がつくったストーリーに沿ってライターが肉付けしたに過ぎないものもあります。
Webメディアの記事では記事にライター名が書かれている「記名記事」がたくさんあります。あのようなものを見ると思わず「ライターがこの記事を全部手掛けたのか、すごいな」と思いがちですが、必ずしもそうではありません。
その裏には企画、取材、執筆、編集、校正まで多くの工程で多くの関係者が関わっており、そこにどれだけライターが関わっているかはわかりません。ライターが提出した原稿に対して編集者が大幅に加筆修正しても、記名記事として出るのはライターの名前です。
コンテンツには執筆と編集の費用がある
この「誰が原稿に関わっているか」という観点は、原稿制作のコスト構造を考える際に非常に重要です。例えばコンテンツマーケティングでは、原稿制作を内製する場合もあれば、外部の個人事業主のフリーランスライターに依頼したり、または制作会社(編集プロダクション)に依頼したりする場合もあります。
原稿にもいろいろ種類がありますが、当社が扱うBtoBコンテンツマーケティングの制作でフリーライターに依頼すれば原稿料は平均的に数万円で済むはずです。ここでは例えばわかりやすく2万円としましょう。一方で全く同じ内容を制作会社に依頼する場合は2万円になりません。ここではわかりやすく10万円になるとしましょう。
では、なぜ8万円も差があるのでしょうか?会社に依頼した場合、その会社内の社員ライターが書く場合もあれば、会社が外部のライターに委託する場合もあります。後者の場合、個人への委託に会社を通すことで手数料的な「中抜き」が発生しているのでしょうか?
もちろん、マージンは含まれますが、主な要素はそれではありません。制作会社の場合は、企画・構成などでライターをディレクションしたり、ライターが執筆した原稿を加筆・修正・校正したりする編集作業が含まれているのです。
少しややこしいのが、「制作会社」と言ってもピンキリであり、すべての会社がそうではないということです。例えばデザイン制作を得意として原稿制作があまり得意でない会社の場合は、制作会社の中に品質の高い編集機能を保持していない場合があります。
こうした企業が執筆の依頼を受けた際は、クライアントに代わって外部のライターを手配する交通整理だけを行うため、多少のマージンだけを載せて原稿料を提案するでしょう。この場合、ライター直接への依頼額と制作会社への依頼額はそこまで変わらないはずです。
この「8万円」を高いと見るか安いと見るか
極論を言うと、個人のライターに依頼すれば原稿はとても安くすみますが、その代わり、依頼主がその品質を評価し、必要であれば自分で直したりライターへ修正を指示したりしなければなりません。つまり自分自身がディレクターになるということです。
一方、原稿をちゃんと確認して的確な修正ができる編集者がいる制作会社に依頼すれば、ライターへ直接発注する場合よりも、品質が担保されて原稿が上がってくる可能性は格段に高まります。
企業のコンテンツ担当者は、原稿料を判断する際にこの部分を着目するべきです。もし自分自身の業務がとても暇であり、ライターに依頼するための企画や構成を自分でじっくり考えたうえで依頼したり、上がってきた原稿を自分で品質の良いものへ直せたりするスキルの自信や余裕があれば、制作会社に執筆を依頼する必要はありません。自分自身が編集者の役割だからです。
しかし、それ以外にやるべき業務があってライターとのやり取りや原稿の確認は最小限にしたい、また原稿の手直しに時間をかけたくないという場合は、少し高い費用を払っても、本業への圧迫といった損失を考えると制作会社へ依頼するほうが妥当です。
企業のコンテンツ担当者は、外注する業者を選定したり、社内への稟議でコストを説明したりする際には、まさにこの点に着目して費用対効果を考えることをおすすめします。
原稿制作で「安物買いの銭失い」は起こりがち
コンテンツ制作でコストを低減したいと思うのはもっともなことです。しかし、コストを気にするがゆえに「安物買いの銭失い」になっているケースは、原稿制作でも非常によく見受けられます。
当社ノーバジェットも、同業他社の情報を詳しくは把握しているわけではないので、他の会社や世間の相場がどうなっているかはあまり分かっていません。しかし、編集力と品質に自信を持っているため、原稿制作費用は決して安いほうではなく、むしろ他社と比べて少し高めではないかと想像しています。
そんな当社に原稿制作をご依頼したお客様の話を聞くと、「納品してもらった原稿を直す必要がないから楽」といったご意見もあれば「過去に個人のライターに依頼したけど、どうも思ったものが上がってこなかった」、「前の制作会社に書いてもらった原稿は修正が大変だった」といったお話も聞きます。
原稿を依頼する際、コストの妥当性を評価する際は、ぜひこの部分に着目してどれだけの価値があるかを考えて評価するのが重要です。
原稿執筆のコスト対効果を高めるには?
では、原稿執筆の際にコストを最適化するにはどうすればよいでしょうか。「良い依頼先を探す」ということは間違いないのですが、それができれば始めから苦労がありません。
1つ確実に言えることは、なるべく複数の依頼先を確保し、適材適所で使い分けるということです。理想的には、編集者による工程が必要ないくらいに一人で完結した品質のものを提供してくれる個人の書き手を探すことです。
当社は制作会社として、さまざまなフリーライターとお付き合いがあります。さきほど原稿は「ライターだけの力ではない」と書きましたが、実は世の中には信じられないくらい圧倒的に上手な原稿を書くライターの場合、完成されすぎて編集者があまり手を加える必要がない場合もあります。
そのようなライターの場合、自分の需要を理解しているので、さきほど「2万円」と書いた金額よりもはるかに高く、制作会社が提示する原稿料に近くはなります。
ただし、残念ながらそのようなライターは数が少ない上に、引っ張りだこであるため、依頼したいときに必ず依頼できるわけではなかったり、もしくは納期が非常に先の日程になってしまったりするデメリットもあります。たくさんの依頼ができないというデメリットがあります。その意味でも、複数の依頼先を確保しておくことが重要です。
また、コンテンツマーケティングは多数のコンテンツが必要になるため、外注だけでコストの限界があり、記事を内製で執筆する体制の構築も検討するべきです。また外部の人間ではなく、社内の人間だからこそ書けることもたくさんあります。
原稿は、執筆の種類やジャンルによって書き手の得意不得意も存在します。コンテンツマーケティングでは、ぜひさまざまな選択肢や依頼先を視野に入れながらコスト効果の高い方法を模索していただければと思います。
▼音声素材などを活かしてコストパフォーマンスよく品質の良い原稿を制作する「AI Pro Writing」もぜひご活用ください。